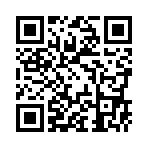2009年01月13日
いけばなの決まりごと
小原流静岡支部の1月定例会&新年会が開催されました
今回は講座で、講師には東京支部より古作厚子先生
今回もダイナミックなお花を教えていただきました
今回は講座で、講師には東京支部より古作厚子先生
今回もダイナミックなお花を教えていただきました
一作目は文人調のお花
中国文人趣味を元にしたお花。
花材は梅、糸芭蕉、仏手柑、オンシジュウム、山鳥の羽
梅には長い徒長枝(”ずあい”といいます)がありますが、
画像では見えませんね(笑)
梅を一木挿しするとき、苔枝、花枝、そしてこの徒長枝で
表現するそうです。
花器の下には「檀座」があり今回は中卓を使用
花器の格というものが有り、黒檀、紫檀の座を「檀座」と言い、
高卓、中卓、平卓の3種があるということ。
今の家はこれだけのお花を飾る場所もないのでなかなか座のある花器を持っていませんが、
知識としてきちっと知ることは大切です。
二作目は花意匠「ひらく」の応用です。
花材は南天、ドラセナインディアナ、アスパラプルモーサス、カスミ草、
アンスリューム、大枝垂れ柳
「柳=家内喜」と表記することもあるそうです。垂れれば垂れるほど良いそうでおめでたいお花。
アレンジの場合は左右対称に花材を入れますが、
いけばなの場合は主、副の関係で主の方に花が多く入ります。
対称軸の中央に客が入りますが、高さの限界と前の張り出しの限界を示すそうで、
それぞれの役割りを確認しました。
花材は南天、ドラセナインディアナ、アスパラプルモーサス、カスミ草、
アンスリューム、大枝垂れ柳
「柳=家内喜」と表記することもあるそうです。垂れれば垂れるほど良いそうでおめでたいお花。
アレンジの場合は左右対称に花材を入れますが、
いけばなの場合は主、副の関係で主の方に花が多く入ります。
対称軸の中央に客が入りますが、高さの限界と前の張り出しの限界を示すそうで、
それぞれの役割りを確認しました。
三作目は琳派のお花
花材は梅、若松、くま笹、
大神楽(椿)、葉牡丹、裏白
松竹梅をあしらい、
祝花では最良とされています。
お正月に門松を立てますが、これは年神様が山から下りてきて、目印になる為に立てるそうです。
また、大神楽という椿は藪椿と扱いが違い、「干菓子を盛るように」いけるということ。
枝を振ってはいけないそうです。
「春夏秋冬に吹く風の美しさを表現する」
改めていけばなの本来の姿を確認した感じです。
まだまだ室礼、花器、道具・・・勉強する文化がいっぱい有ります
この3日間、3つの講演を聴き、その全てが吸収された気がします。
今年は内面にストックする年かな?って思います。
改めていけばなの本来の姿を確認した感じです。
まだまだ室礼、花器、道具・・・勉強する文化がいっぱい有ります
この3日間、3つの講演を聴き、その全てが吸収された気がします。
今年は内面にストックする年かな?って思います。